バレエのバランスの基本とも言えるルティレ(パッセ)。ルティレは回転やデベロッペ、ポーズの形を変える時等に通過するとても大切な形です。きちんとしたルティレを造る、正確なルティレに戻る、このことがバレエの動きの要とも言えます。ルティレの大切な役割の一つは「身体を水平に戻す」ということ。この項ではルティレの注意について記述したいと思います。
とは言え、皆さんは既にレッスンで先生方から沢山のご注意を伺っていることでしょう。ここでは私は今まで私が受けてきたアドバイスや自分が注意している点などを並べることにします。ご自分の意識と比べてみて下さい。
<ルティレ>
まずルティレの呼び方ですが、日本ではルティレのことを「パッセ(passe)」と呼ぶ先生もいらっしゃいます。正確には「パッセ」は“通過”を意味する言葉ですので、「パッセ」とは“ルティレの形を通過する動き”のことを指します。日本では昔からルティレとパッセを混同して使って来ましたので、「ク・ドゥ・ピエ」と「クッペ」のように現在でも同じ意味で使われることが多いのです。ルティレ(retire)の語源はフランス語の"retirer"で「引き出す」や「引き上げる」「引き下ろす」等の「引く」という意味から派生しています。ルティレでの「引く」動作、どことどこを「引く」のか意識しながら動いてみて下さい。
 ルティレは左図の形が基本です。(図では膝横のルティレのようですが膝前のルティエと思って下さい。)
ルティレは左図の形が基本です。(図では膝横のルティレのようですが膝前のルティエと思って下さい。)身体は立体ではなく平たい平面になるイメージを持って下さい。上げた脚の爪先を付ける場所は軸脚の膝の前・横・後と3か所あります。基本として一番多く使われるのは膝前のルティレです。理想としては両膝は180度に開いている角度を取りますが、現実としては膝が完全に180度に開く事はありませんし、開く事を優先して骨盤が前傾してしまっては意味がないので、自分の開く範囲で左右均等に開くことが大切です。理想はあくまでも理想、各個人は身体条件が異なりますので自分の中でより理想の形に近づける努力をすれば良いのです。
ルティレは決して凝り固まった力で身体を固めないように!
各所を伸ばす意識で柔らかく造ります。
各所を伸ばす意識で柔らかく造ります。
(1) 「垂直な軸を作る」
 |
ルティレで最も重要な意識は“芯”の垂直ラインの正確な形成です。 (詳しくは「ルティレ・バランスの垂直」のページをご覧下さい。) 時には動き易さや表現の為に“芯”をオフ・バランス気味にすることもありますが、基本では垂直に立つ事にこだわって下さい。 左図の水色の線は身体の“芯”(軸)を表しています。 “芯”はア・テールなら土踏まずの前寄り、ルルベならば指と指の付け根を基点として、その垂直線上に付け根ポイント(赤い点)と、重心である丹田(緑の点)、頭部が並び、強い力で上下に伸ばされています。 |
(2) 「腿の下側で脚を上げる、軸脚に沿わせて足を上げる」
 |
ルティレの動脚は、常に腿の下側(ピンクの線)で上げたり支えたりしなくてはなりません。腿の下側を使うコツは踵(赤い点)を前へ出すことです。動脚側のお尻を下ろしてしっかりと膝を張り、踵を限界まで前へ出すことで腿の下側は反応して来ます。 5番から脚を上げる時は必ず動足の小指を軸脚の前側に沿わせて脚を上げて行きます(5番プリエからでも同じ)。踵は前に出しますので踵は軸脚には触れていないはずです。軸脚に沿わせて上げることで重心のグラつきを押さえてくれるので、これはとても大切な意識です!骨盤が前や横に大きく傾くと爪先が軸脚から外れることがありますので気を付けましょう。 (爪先を膝横に付けるルティレの時に爪先を軸脚の横側に沿わせて上げる方がいますが、動足は小指を軸脚の前側に沿わせて膝まで上げて、その後に爪先の位置を前から横へ移動させて下さい。) |
(3) 「腰骨を上げてウエストを水平にする」
 |
動脚を上げることに集中すると動脚側のお尻が上がってしまったり、骨盤が大きく傾斜してしまいがちです。骨格としての骨盤はわずかに傾きますが、外から見たウエストは水平を保たなくてはなりません。傾きを防ぐには“芯”を保ったまま軸脚側の腰骨(赤い点)を上へ引上げてみて下さい。 |
(4) 「脇の下を上げて体幹を支える」
 |
上半身は腹筋・背筋と側筋で支えますが、軸を造ることで腹筋・背筋は既に使われているはずです。 側筋は自分で意識しないと中々使えません。側筋とは主に“外腹斜筋”と“内腹斜筋”のことを差しますが、脇の下を正しく引き上げる事で腹斜筋群が胴回りを横側から支えてくれます。この筋肉はピルエット等の回転を行う際にとても大切となる筋肉ですので、きちんと使えるように鍛えましょう。 (「腰筋を上げる」ページの<余談:“側筋”>に側筋の感じ方を記述してあります。) 脇の下を上げるには、まず腕はアン・ナヴァン(前)かアラスゴンド(横)にして(肘は外、小指は起こす)、腕の下に板やバーがあると想像して、上腕部分でその板を上から押して身体が這い上がるようにしてみて下さい(緑の矢印)。脇下が上がり身体の両脇下が外側から押さえられたように感じるはずです(赤い矢印)。その感覚で脇下を上へ上げるようにして下さい。慣れてくれば腕がアン・オー(上)の時は肩甲骨を下げる事で両脇が同じように使えるようになります。 |

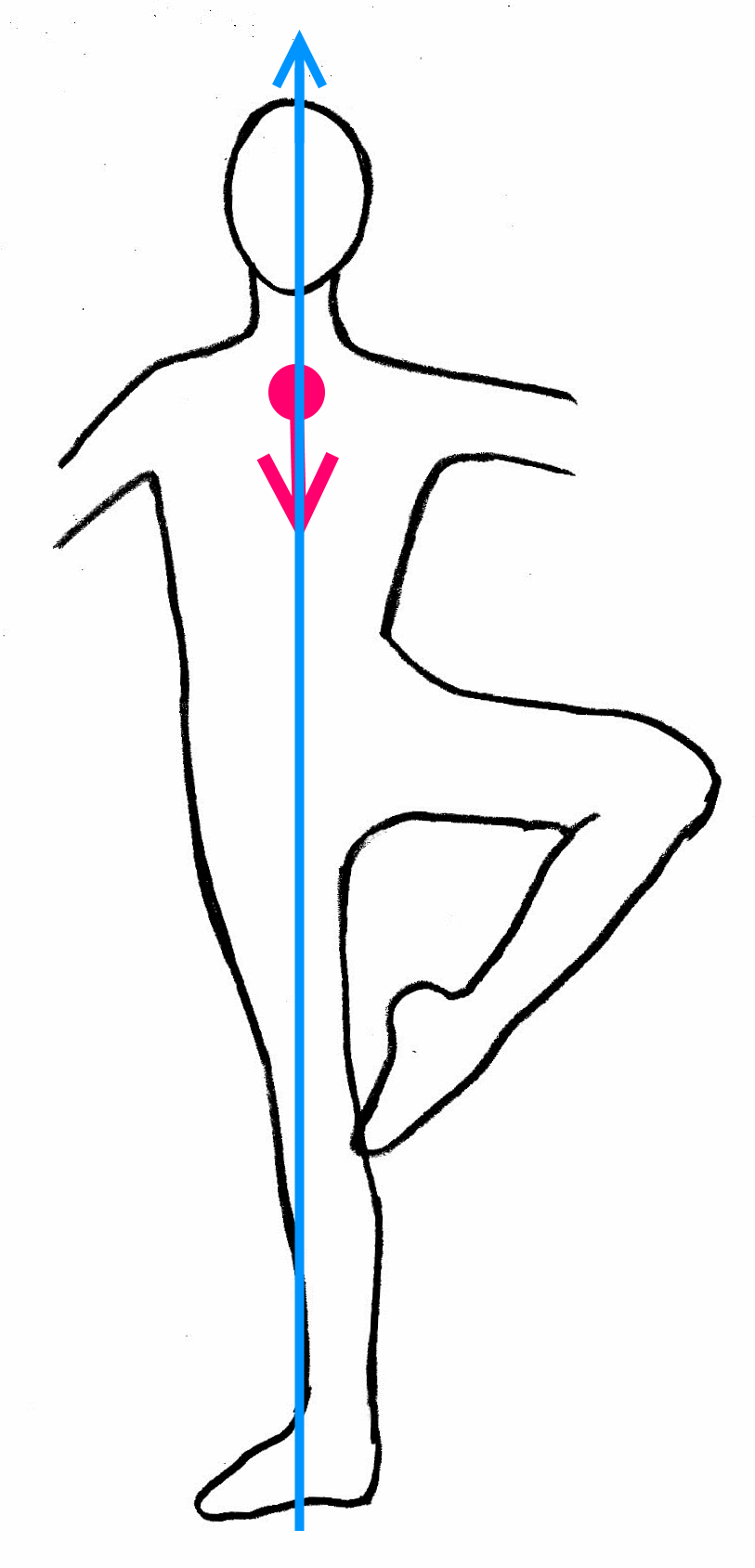
|
先程記述した通り、ルティレの大きな役割の一つに「身体の水平を取り戻す」という役割があります。どんなに傾いた後でも5番やルティレに戻る時は水平を取り戻すという意味です。基本の形の上では両肩、両脇、ウエストは水平(緑の点線)。 横に張った膝は、軸脚に対して膝を真横に張る(引く)ように水平を感覚として保ちます(オレンジの矢印)。 安定した“軽い”ルティレを造るには、ある一定以上の高い位置まで身体が引き上がっていなければなりません。私の感覚では「雲の上に出る」という感覚なのですが、ある先生では「両脚の張りの上に居続ける」感覚だそうで、その感覚は人それぞれです。 とにかく上へ身体を持ち上げる為には何かテコになるような物を押して上へ這い上がると楽に上がれるようです。そのテコとする部分を私の場合は腰と上腕の部分なのですが、人によっては脚や脇だったりするようです。または、背中の僧帽筋(ピンクの点)を下ろす力を利用することも良いでしょう。何か上から軽く押さえたり下ろしたりする下向きの力を利用して上へ這い上がることは、安定した“引上げ”を得るひとつの手段です。 |
(6) 「両側の付け根ポイントをしめる」
 |
“芯”となる垂直線を上手に引き上げる(押上げる)ことが出来たら、骨盤底にある両側の付け根ポイントをしめて(閉じて)、身体の重みが落ちて来ないようします。 これは大殿筋のようなお尻の上部にある大きな筋肉をしめて身体を支えるのではなく、ごく“芯”に近い所にある“ハムストリングの付け根ポイント”をしめて“芯”を支えるようにします。(軸脚側の付け根ポイントは“芯”とほぼ同じライン上になります。(1)の図を参照) |
以上がルティレを水平に保つコツですが、他にも背中の意識(「肩甲骨下のラインを垂直に保つ」等)も利用すると良いと思います。また腕についても、腕はただ付けているだけではなく上手に利用するべきです。(「上へ上げた腕は頭上の何かをつかんでいるように」、「前へ出した腕は手でみぞおち前の何かをつかんでいるように」、etc)
ルティレ・バランスでは垂直線を、ルティレでは水平の感覚を、意識しました。回転するピルエットではこれらに加えて「ひねりによる起動力」と「首の返しによる送り」が必要となって来ます。まずは垂直と水平をしっかり身につけましょう!これらはバレエのテクニックにおいては共通するテーマです。
どれほど長くバランスを取っていられても、どれほど脚を開けていても、観ていて美しくなければ意味がありませんし、「我慢」を見せられては興ざめです。繰り返しますが、バレエは伸びと軽やかさ、美しさです!「力任せバレエ」にはならないように注意してレッスンしましょうね。